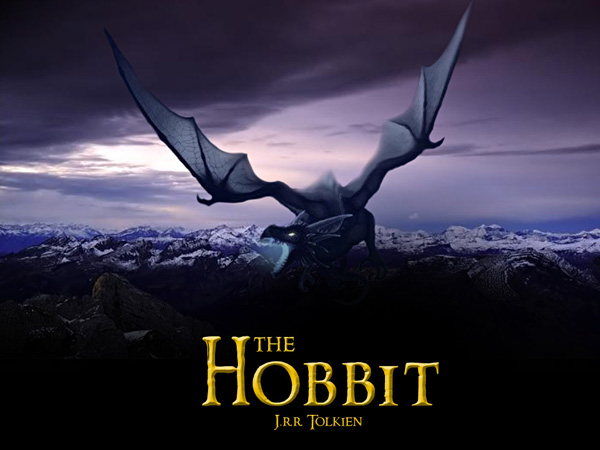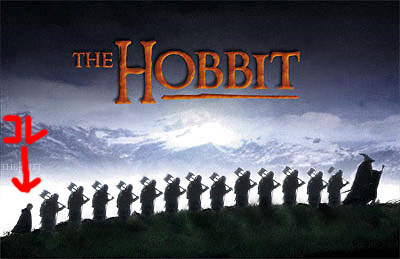この小文は、帝都の書店で偶然発見した、「アヌアドの子ら(A Children's Anuad)」という古めかしい書物に記されていた事柄をまとめたものである。
タムリエル(Tamriel)の創世には諸説あるが、アヌアドは神話時代(the Mythic Era)から伝わる創世記(The Anuad creation myth)の一つだ。しかしながらアヌアドそのものは難解な太古の言語で記されており、この「アヌアドの子ら」はそれを意訳(The Anuad Paraphrased)して書かれたもので、いたって簡素な物語となっている。
【中略】
興味深いのはエルフ種の成り立ちである。以下、原文を抜粋する。
Over many years, the Ehlnofey of Tamriel became:
長い時を経て、タムリエルのエルノフィは次のように変化した。
- the Mer (Elves),
メア(エルフ)、
- the Dwemer (the Deep Ones, sometimes called Dwarves),
ドゥエマー(深きもの、ときにドワーフと呼ばれる)、
- the Chimer (the Changed Ones, who later became the Dunmer),
チャイマー(変化したもの、のちにダンマーとなった)、
- the Dunmer (the Dark or Cursed Ones, the Dark Elves),
ダンマー(闇の、または呪われたもの、ダークエルフ)
- the Bosmer (the Green or Forest Ones, the Wood Elves), and
ボスマー(緑の、または森のもの、ウッドエルフ)、そして
- the Altmer (The Elder or High Ones, the High Elves).
アルタマー(古の、または高きもの、ハイエルフ)
以上である。
・・・・・なんちゃってw
や、何が言いたいかといえば、エルフに対して細かな設定をしているファンタジーは多いかもしれませんが、ボスマーやダンマーといった新しい名称を作っちゃったゲームというのは、そうそう無いんじゃないか、と。(そういえば、確かD&Dではホビットという名前を版権的に使用できなくって、ハーフリングって名前になってたような。あがおご・・・)
ちなみに、「A Children's Anuad」のなんちゃって考察文は
こちらからどうぞw
まぁ、それはともかく、Skyrimのいくつかの種族のSSがアップされてたので貼り貼りします(`・ω・´)
ノルド
http://farm7.static.flickr.com/6144/6036630186_b097ea1eaa_o.jpg ノルド女
http://pcmedia.ign.com/pc/image/article/117/1172982/e3-2011-elder-scrolls-v-skyrim-screenshots-20110606000856758.jpg ボスマー(もしかすると色の白いダンマー)
http://www.tesnexus.com/imageshare/images/422514-1313174800.jpg ダンマー
http://cdnstatic.bethsoft.com/bethblog.com/wp-content/uploads/2011/08/darkelf.jpg オーク
http://pcmedia.ign.com/pc/image/article/116/1162158/the-elder-scrolls-v-skyrim-20110415033053299.jpg これもオーク(相当肌の色がいじれるのかな?)
http://www.tesnexus.com/imageshare/images/422514-1313172495.jpg カジート
http://www.tesnexus.com/imageshare/images/422514-1313172607.jpg カジート(これも肌の色が違う。同種族なのか、別種族扱いなのか)
http://www.tesnexus.com/imageshare/images/422514-1313172671.jpg アルゴニアン
http://www.tesnexus.com/imageshare/images/422514-1313172305.jpg レッドガード
http://img.jeuxvideo.fr/03D4022604498820-c1-photo-oYToxOntzOjE6InciO2k6OTgwO30%3D-the-elder-scrolls-5-skyrim.jpg これもノルドらしい(100% confirmed by Gstaff to be a Nordとのこと)
http://dl.dropbox.com/u/8613775/Skyrim/SkyrimNord/skyrim_kaysercharacter.jpg ・・・どっちかといえば一番下のはボスマーのイメージに近い気ガス。
でも、どうやら色々いじれるって考えたほうがよさげで、これはもう、wktkが止まらんです(*´Д`)ハァハァ
で、下は「QuakeCon 2011」でのSkyrimのデモプレイの様子。
以前の「E3」でのデモプレイと大きな違いはないですが、少し長めにプレーしてますね。ちょっと観客の声に答えてたりw
SSにしてもこのデモにしても、箱版らしいので、PC版はさらに美しくなると考えて良いかも。
QuakeCon 2011 - The Elder Scrolls 5 : Skyrim... 投稿者 Xboxlivefr
テーマ:The Elder Scrolls V: Skyrim - ジャンル:アダルト
- 2011/08/14(日) 20:56:34|
- Skyrim: 雑記
-
| トラックバック:0
-
| コメント:4
この小文は、帝都の書店で偶然発見した、「アヌアドの子ら(A Children's Anuad)」という古めかしい書物に記されていた事柄をまとめたものである。
タムリエル(Tamriel)の創世には諸説あるが、アヌアドは神話時代(the Mythic Era)から伝わる創世記(The Anuad creation myth)の一つだ。しかしながらアヌアドそのものは現在入手不可能であり、恐らく難解な太古の言語で記されているだろうが、この「アヌアドの子ら」はそれを意訳(The Anuad Paraphrased)して書かれたもので、いたって簡素な物語となっている。
物語は世界開闢から始まる。
アヌ(Anu)とパドメイ(Padomay)という兄弟が虚空(the Void)から生まれ出で、そして時が刻み始めたという。兄弟が虚空を漂ううち、最初の女性であるニア(Nir)が光と闇の狭間に出現する。
兄弟はニアを愛すが、ニアが選んだのはアヌの方であった。失意のパドメイは一旦は二人のもとを去るが、結局争いとなり、ニアはアヌとの子、「創造(Creation)」を生んだのち、パドメイに負わされた傷がもとで死ぬ。
ニアが生んだ「創造」は12の創造世界(the twelve worlds of creation)となり、生命が誕生し栄えたが、嫉妬に狂ったパドメイがこれを断ち切り破壊する。アヌは12の世界の欠片をつなぎ合わせたが、争った二人はともに時の外に飛ばされてしまう。こうして生まれたのがニルン(Nirn)、すなわちタムリエルの世界(the world of Tamriel)である。
この争いのとき流れたパドメイの血はデイドラ(Daedra)となり、アヌの血は星々となり、二人の混じり合った血はエイドラ(Aedra)になった。(その為、エイドラは善と悪の両面を持ち、「創造」と関係のないデイドラよりも地上の事柄に大きな関心を持つという)
欠片をつなぎ合わせて作られたニルンは混沌とし、生き残った生命はエルノフィ(Ehlnofey)種とヒスト(Hist)種のみであった。エルノフィ種はメア(Mer)とメン(Men)=ヒトの祖先となった。ヒスト種はアルゴニア(Argonia)の樹木となった。
比較的無傷であった大きな欠片に住むエルノフィ種は古エルノフィ(Old Ehlnofey)となって、その後、メアの先祖となった。それ以外のエルノフィ種はつぎはぎだらけのニルンをさまよい、古エルノフィの土地にたどりつき、その繁栄を目にする。そして戦争が起きる。高度な文明を築いていた古エルノフィにとって、さまよえるエルノフィは同胞として受け入れがたかったのだ。
この戦争でニルンの多くの土地が海に沈み、現在の大陸であるタムリエル、アカヴィア(Akavir)、アトモラ(Atmora)、ヤクダ(Yokuda)が残った。さまよえるエルノフィ種はタムリエル以外の3大陸に散らばり、ヒトとなった。
興味深いのはエルフ種の成り立ちである。以下、原文を抜粋する。
Over many years, the Ehlnofey of Tamriel became:
長い時を経て、タムリエルのエルノフィは次のように変化した。
- the Mer (Elves),
メア(エルフ)、
- the Dwemer (the Deep Ones, sometimes called Dwarves),
ドゥエマー(深きもの、ときにドワーフと呼ばれる)、
- the Chimer (the Changed Ones, who later became the Dunmer),
チャイマー(変化したもの、のちにダンマーとなった)、
- the Dunmer (the Dark or Cursed Ones, the Dark Elves),
ダンマー(闇の、または呪われたもの、ダークエルフ)
- the Bosmer (the Green or Forest Ones, the Wood Elves), and
ボスマー(緑の、または森のもの、ウッドエルフ)、そして
- the Altmer (The Elder or High Ones, the High Elves).
アルタマー(古の、または高きもの、ハイエルフ)
以上である。
ヒトは3つの大陸で、それぞれ、アトモラのノード人(Nord)、ヤクダのレッドガード人(Redguard)、アカヴィアのツァエシー人(Tsaesci)となっている。
ヒスト種はこの戦争と関係はないが、戦禍によりタムリエルのブラックマーシュ(Black Marsh)となったもの以外は、ほとんど海に沈んだ。
その後、ヒトは再びタムリエルに現れる。すなわち伝説的なイスグラモア(Ysgramor)に導かれたノード人のスカイリム(Skyrim)征服である。ノードらは有史以前のタムリエル北部の海沿いに定住し、イスグラモアの血を引く13代目の王、ハラード(King Harald 1E113-221)が、歴史上の記録に残る最初の人物として現れる。こうして神話時代が終わりを告げた。
以上が「アヌアドの子ら」のおおよその顛末である。繰り返しになるが、「アヌアド創世記」そのものはもはや入手不可能である為、この本がどこまで原典に近いかは分からない。しかしながらデイドラ及びエイドラの神々の誕生や我々ヒトやエルフ達の起源を知る上で、興味深いものがある。書店で見つけたときは、是非とも手にとって頂きたい一冊である。
Last Seed 27 3rd Era 433
IC,Talos Plaza District
Sumner
筆者注:帝国語からアカヴィア語に翻訳するにあたり、固有名詞はなるべく帝国語に近いものを選んだ。私は帝都に住んでからまだ日が浅い為、友人の
グーグル(Google)君の発音に頼るところが大きい。この場を借りて厚く御礼を申し上げる。
・・・・以上、ニルンの神話についてのなんちゃって考察でしたw
あ、でも「A Children's Anuad」自体はゲーム中にちゃんと存在しますので、ご一読をお勧めします。ゲームに深みが増しますよ~(`・ω・´)
- 2011/08/14(日) 20:54:55|
- TES Sumner's Tales
-
| トラックバック:0
-
| コメント:2